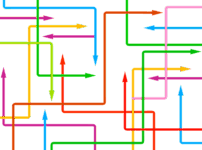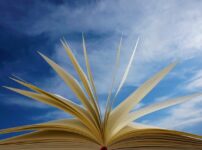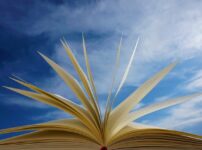当サイトのご訪問ありがとうございます。
当サイトは会計・税務の概要の理解に特化したサイトなります。
当サイトは以下のような方に適しています。
1.簿記の勉強をはじめたい方
2.決算書という言葉聞いたことはあるが、見方がわからない方
3.会計又は税務の概要を理解したい方
4.会計・税務を勉強するためのまとまった時間が取れない方
5.すぐに会議で会計・税務に関する基礎知識を必要とする方
6.特定の個別論点の概要を知識を知りたい方
また当サイトではAIでは書くことのできない、公認会計士であるサイト運営者の実体験に基づく実務上のポイントも記載させていただいております。
当サイトの構成は以下の通りです(リンクがないものは仕掛中)。
■貸借対照表
Ⅰ.流動資産
・現金及び預金
・受取手形
・売掛金
・契約資産
・有価証券
・商品及び貯蔵品
・仕掛品
・原材料及び貯蔵品
・前払費用
・その他流動資産
・貸倒引当金
Ⅱ.有形固定資産
・建物
・構築物
・機械及び装置
・車両運搬具
・工具、器具備品及び備品
・土地
・リース資産
Ⅲ.無形固定資産
・ソフトウェア
・のれん
・電話加入権
Ⅳ.投資その他の資産
・投資有価証券
・関係会社株式
・長期貸付金
・繰延税金資産
Ⅴ.繰延資産
・社債発行費
・長期前払費用
Ⅵ.流動負債
・支払手形
・買掛金
・短期借入金
・リース債務
・未払金
・未払費用
・未払法人税等
・契約負債
・前受金
・預り金
・前受収益
・賞与引当金
Ⅶ.固定負債
・社債
・長期借入金
・長期リース債務
・退職給付引当金
・資産除去債務
Ⅷ.純資産
・資本金
・資本剰余金
資本準備金
その他資本剰余金
・利益剰余金
利益準備金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金
・自己株式
・その他有価証券評価額金
・繰延ヘッジ損益
・新株予約権
当サイトを利用していただきぜひ、会計や税務に関する疑問の解消や知識を深めていただき、仕事や勉強に活かしていただければ幸いです。
なお、こう言ったテーマについても掲載してほしい等のご要望あれば、下記の「問い合わせフォーム」よりお問い合わせください。
ご要望の多いものから順次対応させていただきます。
【最新の投稿記事】
新リース会計の基礎を理解する!新リース会計基準の用語の定義を徹底解説
新リース会計基準の主要用語 新リース会計基準は、2027年4月1日以後開始する連結会計年度及び事業年度の期首から強制適用となる企業会計基準第34号「リースに関する会計基準(以下、「リース会計」という。)」および企業会計基準適用指針第33号「リースに関する会計基準の適用指針(以下、「リース適用指針」という)は、特に借手側の会計処理に大きな変更をもたらします。 具体的には借手側では、今まで、オフバラ可能だったリース契約もオフバラが認められなくなるといった変更があるかと考えています。 この新しい基準を正しく適用 ...
ReadMore
新リース会計基準でオンバランスされるリース契約!?リースの識別とはどういうこと?
上場企業、会社法上の大会社等は、2027年4月1日以降に開始する連結会計年度及び事業年度の期首から企業会計基準第34号リース会計に関する会計基準及び企業会計基準適用指針第33号リースに関する会計基準の適用指針(以下、総称して「新リース会計基準」という。)が強制適用されることとなります。 既に新リース会計基準の適用をされている会社、新リース会計基準の適用準備をしている会社、新リース会計基準を適用されるのかどうかを検討されている会社等、様々な状況にあるかと思います。 そんな新リース会計基準ですが ...
ReadMore
【五十音順】英語の勘定科目はこれさえ押さえておけば間違いない!基本的な勘定科目一覧の決定版!!
英語の勘定科目一覧 国際会計基準(IFRS)の導入が広がっている昨今において、皆様のなかには、英語の決算書を読まなければならない方や英語で決算書を作らなければならない方もいらっしゃるかと思います。 本記事は、代表的な勘定科目について五十音順に記載したものです。 なお、流動資産、固定資産、流動負債、純資産に区分については、リンクをご参照ください。 カッコ内は、別の表現を記載したものとなりますので、そちらもご参考にしてください。 あ行 ・預り金:With ...
ReadMore
英語の勘定科目の一覧!基本的な勘定科目は、これを押さえておけば間違いない!
英語の勘定科目一覧 国際会計基準(IFRS)の導入が広がっている昨今において、皆様のなかには、英語の決算書を読まなければならない場面や、英語で決算書を作らなければならない方もいらっしゃるかと思います。 とはいえ、勘定科目は多岐にわたるため、全てを網羅的に記憶するのが難しいというのも事実です。 本記事は、代表的な勘定科目について流動資産、固定資産、流動負債、純資産に区分して英語の勘定科目を一覧にして記載しておりますので、参考にしていただければ幸いです。 なお、上記の区分とは別に以下のリンクでは ...
ReadMore
法人税法上の完全支配関係
法人税法上の完全支配関係とは 法人税法における完全支配関係がある場合、グループ法人税制(グループ法人単体課税制度)の強制適用を受けることとなります。では、法人税法上における完全支配関係とは、どのようなものをいうのでしょうか。法人税法第2条12の7の6では以下のように規定されています。 法人税法第2条12の7の6 完全支配関係 一の者が法人の発行済株式等の全部を直接若しくは間接に保有する関係として政令で定める関係(以下この号において「当事者間の完全支配の関係」という。)又は一の者との間に当事者間の完全支配の ...
ReadMore
簡易課税制度②
簡易課税制度の選択 簡易課税制度とは中小事業者の納税事務負担に配慮する観点から、事業者の選択により、売上げに係る消費税額を基礎として仕入れに係る消費税額を算出することができる制度です。 簡易課税制度を選択するために以下の要件をすべて満たす必要があります。 ①消費税の課税事業者であること ②基準期間(通常であれば前々期)の課税売上高が5,000万円以下であること ③事前に納税地の所轄税務署長に「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出していること 上記の要件をすべて満たした場合のみ、簡易課税制度の適用が認められ ...
ReadMore
簡易課税制度①
簡易課税制度とは 簡易課税制度とは中小事業者の納税事務負担に配慮する観点から、事業者の選択により、売上げに係る消費税額を基礎として仕入れに係る消費税額を算出することができる制度です。 インボイス制度の導入が決定して以降、インボイス制度の適用を受けることになった個人事業主又は法人の消費税に対する関心は相対的に上がり、消費税申告書が増加することが見込まれています。 消費税申告のうち原則的方法により申告を行うには、課税売上げと課税仕入れ等を正確に区分する必要がありますが、当該区分にはある程度正確な知識が必要とな ...
ReadMore
消費税の計算構造
消費税とは 消費税とは、簡単にいうと消費する人負担する税金で、皆様にとって最も身近な税金かと思います。 一般的に消費税と言われ場合、税率10%や8%を思い浮かべるかもしれませんが、厳密には消費税は国税部分の消費税と地方消費税に区分されることとなります。 消費税及び地方消費税に区分されます。消費税が計算され、当該消費税額に基づき地方消費税の金額が決定します。具体的には以下のように区分されています。 区分 標準税率 軽減税率 消費税率 7.80% 6.24% 地方消費税率 2.20% 1.76% 合計 10. ...
ReadMore
消費税申告
消費税及び地方税の申告書について 消費税法は、厳密には消費税及び地方消費税に区分されます。消費税が計算され、当該消費税額に基づき地方消費税の金額が決定します。 消費税法では課税事業者になると、その課税事業者は課税期間ごとに、当該課税期間の末日の翌日から2か月以内に、次に掲げる事項を記載した申告書を税務署長に提出しなけばならないとしていいます(消費税法第45条第1項)。 ただし、課税事業者であっても、国内おける課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れがなく、かつ納付すべき消費税額がない課税期間については税務署への ...
ReadMore
法人税申告書
確定申告と法人税申告書 内国法人は、事業年度が終了した後に決算を行い、株主総会等の承認を受け、その承認を受けた決算(確定決算)に基づいて所得金額や法人税額等、法人税法に定められた事項を記載した申告書を作成し、これを納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません。 この手続を「確定申告」といい、こうして作成された申告書を「確定申告書」といい、法人が法人税を納めるための確定申告書を法人税申告書といいます。 なお、欠損のため納付すべき法人税の額がない場合や休業中の場合であっても確定申告書を提出する必要があります ...
ReadMore